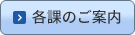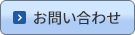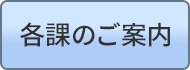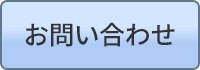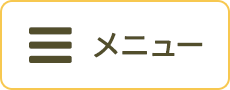小児用肺炎球菌
生後2か月になったら、なるべく早く受けましょう。
対象者・接種スケジュール
◆対象者:生後2か月から5歳のお誕生日の前日までの者
◆接種スケジュール
生後2か月から6か月で開始する場合
標準的には生後12か月までに27日以上の間隔で3回接種後、60日以上あけて1歳以降に1回追加接種(追加接種は標準的には生後12~15か月で受ける)
ただし、初回2回目、3回目の接種は生後24か月までに行い、2回目が生後12か月を超えた場合、3回目は行わない。(追加接種は可能)
生後7か月から11か月で開始する場合
標準的には生後12か月までに27日以上の間隔で2回接種後、60日以上あけて1歳以降に1回追加接種
ただし、初回2回目の接種は生後24か月までに行い、それを超えた場合は行わない。(追加接種は可能)
1歳から2歳未満で開始する場合:60日以上の間隔で2回接種
2歳から5歳未満で開始する場合:1回接種
ワクチンについて
令和6年10月から、使用するワクチンが沈降15価肺炎球菌結合型ワクチンから沈降20価肺炎球菌結合型ワクチンに変更されました。ただし、当分の間は沈降15価肺炎球菌結合型ワクチンも使用することができます。
原則として最初に接種したワクチンと同一のワクチンで接種を完了させてください。ただし、やむを得ない事情により同一ワクチンで接種できない場合は、残りの回数を別のワクチンで接種しても差し支えありません。
受け方
◆接種方法:皮下注射 ・筋肉注射
◆持ち物:母子健康手帳・予診票
◆費用:無料
◆実施場所:市内指定医療機関(下記参照)
令和7年度市内指定医療機関一覧 (PDFファイル: 116.8KB)
病気とワクチンの副反応について
◆小児の肺炎球菌感染症について
肺炎球菌は肺炎だけでなく感染する身体の部位によって様々な症状を引き起こします。中でも「細菌性髄膜炎」は頻度が高く、乳幼児が感染すると重症化しやすく後遺症を残すこともあるため問題とされています。髄膜炎は、発熱、嘔吐、けいれんなどの初期症状ではじまります。肺炎球菌による髄膜炎の発症は、特に2歳未満の乳幼児においてリスクが高いといわれています。発症の予防には、ワクチン接種が効果的です。
◆肺炎球菌ワクチンの副反応について
接種部位の局所反応として赤い発しんが出たり、腫れたり、しこりができたりすることがありますがおおむね軽度です。全身的な副反応としては、発熱、易刺激性、傾眠状態などがみられることがあります。きわめてまれに、アナフィラキシー様症状、けいれん、血小板減少性紫斑病などの報告があります 。
注意事項
◆接種に行く前の注意事項
注意1:予診票をお持ちでない方は、こども家庭課窓口でお渡しいたします。
注意2:接種の際は、お子さんの状態をよく知る保護者の方が必ず同伴してください。
注意3:やむを得ず高石市外の医療機関で接種する場合は、必ず事前にこども家庭課までご相談ください。
◆接種を受けることができない人
1:明らかに発熱のある人(通常37.5度以上)
2:重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
3:麻しん・風しん・水ぼうそう・おたふくかぜなどの伝染性の病気にかかって、治ゆ後4週間程度経過していない人
4:突発性発疹・手足口病・伝染性紅斑などの伝染性の病気にかかって、治ゆ後1から2週間程度経過していない人
5:接種予定の予防接種液の成分によってアナフィラキシーを起こしたことがある人
6:けいれんをおこして3か月経過していない人
7:その他、医師が不適当な状態と判断した人
◆接種を受けた後の注意
1:接種を受けた後30分間は、接種医療機関と連絡が取れるようにしてください。
2:接種後1週間は副反応の出現に注意してください。
3:接種後は接種部位を清潔にしてください。
4:接種当日の入浴は差し支えありませんが、注射した部位をこすらないようにしてください。
5:接種当日の過度な運動は避けてください。
6:他の種類のワクチンを接種する場合、接種間隔の制限はありません。
7:高熱・けいれん・意識不明などの異常な症状が出た時は、すぐに医師の診察を受けてください。なお、医師の診察を受けた場合は必ずこども家庭課へご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
教育部 こども未来室 こども家庭課 こども家庭係
〒592-8585
大阪府高石市加茂4丁目1番1号
電話:072-267-1160 ファックス番号:072-265-1015