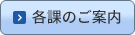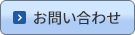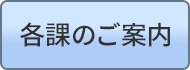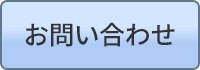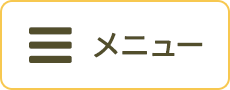平成29年度から変更される個人住民税(市・府民税)の主な内容
給与所得控除の見直し
給与所得の算出方法が変更され、給与所得控除額の上限額が段階的に引き下げられることとされました。平成28年度(平成27年分)までは、給与所得控除の適用上限が給与収入1,500万円(控除額245万円)でしたが、平成29年度(平成28年分)は1,200万円(控除額230万円)に、平成30年度(平成29年分)以降は1,000万円(控除額220万円)に引き下げられます。
給与所得控除額の上限が適用される給与収入と給与所得控除額
| 課税年度 |
給与収入 (上限額) |
給与所得控除額 (上限額) |
| 平成28年度(平成27年分)以前 | 1,500万円 | 245万円 |
| 平成29年度(平成28年分) | 1,200万円 | 230万円 |
| 平成30年度(平成29年分)以降 | 1,000万円 | 220万円 |
例)給与収入1,300万円の場合
平成28年度(平成27年分)の給与所得:1,300万円-245万円=1,055万円
平成29年度(平成28年分)の給与所得:1,300万円-230万円=1,070万円
平成30年度(平成29年分)の給与所得:1,300万円-220万円=1,080万円
給与所得者の特定支出控除の見直し
上記引き下げに伴い、給与所得者の特定支出控除も変更されることとなりました。前年中の特定支出合計額が給与所得控除額の2分の1を超える場合は、その超える額を給与所得控除額に加算されます。
給与所得者の特定支出控除額
| 給与収入金額 | 適用判定の基準となる特定支出の合計額 | |
| 現行(平成28年度まで) | 変更後(平成29年度以降) | |
| 1,500万円以下 | 給与所得控除金額×1/2 | 給与所得控除額×1/2 |
| 1,500万円以上 | 125万円 | 給与所得控除額×1/2 |
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化
日本国外に居住する親族に係る配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除(16歳未満の扶養親族を含む)の適用を受ける方について、所得税の確定申告や市・府民税申告、給与支払者及び公的年金等の支払者に扶養親族等申告書等を提出する際に、親族関係書類及び送金関係書類を添付または提示することが義務付けられました。
(注意)給与支払者や年金支払者に国外居住親族(16歳未満の扶養親族含む)に係る親族関係書類及び送金関係書類を扶養控除等申告書に添付または提示をしている場合は、所得税の確定申告や市・府民税申告に親族関係書類及び送金関係書類を添付または提示をする必要はありません。
・親族関係書類とは
次の(1)または(2)のいずれかの書類(当該書類が外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文を添付しなければならない)で、国外居住親族が納税者の親族であることを証明するものをいいます。
(1)納税者の国外居住親族が日本人である場合
戸籍の附票の写し、国または地方公共団体が発行した書類及び当該国外居住親族の旅券の写し
(2) 納税者の国外居住親族が外国人である場合
外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(その国外居住親族の氏名、生年月日及び住所の記載があるものに限る)。
・送金関係書類とは
次の(1)または(2)の書類(当該書類が外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文を添付しなければならない)で、その国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払を必要の都度行ったことを明らかにするものをいいます。
(1)金融機関の書類またはその写しで、金融機関が行う為替取引により、納税者から、その国外居住親族に支払をしたことを明らかする書類(送金依頼書など)
(2)クレジットカード発行会社の書類またはその写しで、クレジットカード発行会社が交付したカードを提示して、その国外居住親族が商品等を購入したこと、及びその商品購入代金に相当する額を納税者から受領したことを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)
金融所得課税の一体化
金融所得課税の一体化として、公社債等の課税方式を株式等の課税方式と同一化することとなりました。
・特定公社債等及び一般公社債等について
公社債等について、次のとおり特定公社債等と一般公社債等に区分されることとなりました。
特定公社債等:国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債など
一般公社債等:特定公社債等以外の公社債など
・公社債等に係る利子等について
公社債等に係る利子等は、源泉分離課税(府民税利子割5%)とされていましたが、平成28年1月1日以降に支払を受けるべき利子等について、次のとおりに変更されました。
特定公社債等:源泉分離課税(府民税配当割5%)した上で、申告分離課税(市民税3%、府民税2%)を選択できるようになりました。なお、申告分離課税を選択した場合、合計所得金額(扶養控除や市・府民税の非課税判定に使用する金額です。)の対象となります。
一般公社債等:源泉分離課税(府民税5%)のまま、変更はありません。
・公社債等に係る譲渡所得等について
公社債等に係る譲渡所得等については、これまで課税されないこととされていましたが、平成28年1月1日以降に譲渡をした場合、次のとおりに課税されることとなりました。
特定公社債:上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税(市民税3%、府民税2%)とすることとされました。ただし、源泉徴収ありを選択している特定口座内の特定公社債等に係る譲渡所得等の金額については、申告する必要はありません。
一般公社債等:一般株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税(市民税3%、府民税2%)とすることとされました。
・損益通算及び繰越控除の対象について
株式等に係る譲渡所得等との損益通算及び繰越控除をすることができる対象について、平成29年度以降の市・府民税から、次のとおり見直すこととされました。
上場株式等及び特定公社債等に係る譲渡所得等の損益通算及び繰越控除:上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等と、特定公社債等に係る利子所得等及び譲渡所得等との損益通算をすることができることとされました。また、その年に損益通算をしても控除しきれない損失の金額については、繰越控除をすることができることとされました。ただし、上場株式等に係る配当所得等及び特定公社債等に係る利子所得等については、申告分離課税を選択したものに限り、損益通算及び繰越控除をすることができます。
一般株式等及び一般公社債等に係る譲渡所得等の損益通算:一般株式等に係る譲渡所得等と一般公社債等に係る譲渡所得等との損益通算をすることができることとされました。
上場株式等及び一般株式等に係る譲渡所得等の損益通算及び繰越控除:平成28年度までの市・府民税では、上場株式等に係る譲渡所得等と一般株式等に係る譲渡所得等との損益通算をすることができましたが、平成29年度以降の市・府民税では、損益通算をすることができないこととされました。
また、平成28年度以前の各年度において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額で、平成29年度以降に繰り越されたものについても、一般株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越控除をすることができないこととされました。
上場株式等の譲渡所得等及び配当所得等の申告・課税方法について
・株式等の配当所得等の申告・課税方法について
個人が法人などから受け取る株式等の配当等は、配当所得として他の所得(給与所得や不動産所得など)とあわせて、総合課税の扱いとして課税されますが、上場株式等の配当所得等については、特例として、配当等が支払われる際に「道府県民税配当割」が他の所得と分離して課税され特別徴収されます。「道府県民税配当割」の特別徴収により課税関係が終了するため、上場株式等の配当所得等の申告は必要ありません(申告不要制度)が、各種所得控除等の適用を受けるために、総合課税または申告分離課税を選択して申告することもできます。
申告された上場株式等の配当所得等は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険料・介護保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご留意ください。
なお、税額決定通知書・納税通知書が発送される日までに、確定申告書とは別に、市民税府民税申告書をご提出いただくことにより、所得税と異なる課税方法(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択できます。(例:所得税は総合課税、個人市・府民税は申告不要制度)
・株式等の譲渡所得等の申告・課税方法について
個人が株式等を譲渡した場合の譲渡所得等に対する所得割については、他の所得と分離して課税され、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得等に対しては、「道府県民税株式等譲渡所得割」が課税され特別徴収されます。「道府県民税株式等譲渡所得割」の特別徴収により課税関係が終了するため、上場株式等の譲渡所得等の申告は必要ありませんが、各種所得控除等の適用を受けるために申告することもできます。
申告された上場株式等の譲渡所得等は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険料・介護保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますのでご留意ください。
なお、税額決定通知書・納税通知書が発送される日までに、確定申告書とは別に、市民税府民税申告書をご提出いただくことにより、所得税と異なる課税方法(申告不要制度、申告分離課税)を選択できます。(例:所得税は申告分離課税、個人市・府民税は申告不要制度)